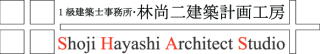ESSAY-住宅について
□ 「いい住宅」?
以前、施主から紹介されて「”いい住宅”が欲しい」という本を読んだことが
あります。その当時ベストセラーになっている本だということでした。一般
ユーザー向けのこういう本はほとんど読んだことがなかったので、興味津々
読み始めたところ、もうびっくり仰天その内容は一言、いい住宅とは外断熱、
外壁二重通気工法の住宅にかぎる!というものでした。ただこれだけの事で
一冊の本を、くだくだ書いたのも恐れ入りましたが、「いい住宅」が、外断熱、
通気工法という結論にもならない結論に、呆然としてしまいました。
我々、建築設計を業としているものにとって、外断熱、外壁通気工法は、
新しいものでもなんでもなく、ずいぶん以前からいろんな人が試行錯誤して
いる工法で、断熱効果という意味では、有効な工法であることは間違いあり
ません。ただ「いい住宅」=断熱効果だ、と考えている設計者はほとんど
いないと思います。
自然環境保全への配慮、エコロジーとかの現在の風潮に合わせて、
ハウスメーカーは高断熱、高気密を商品の”ウリ”として広告をしています。
住宅のPLAN(間取り)がほぼ、どこのメーカーも大差ないような状況になって
きているいま、商業戦略としたら、それも理解できるものではあります。
しかし、住宅のあり方として、断熱性能、気密性能が第一義になるのは、
やはりどこかおかしな風潮だと思わざるをえません。
我々設計者にとって、一番大切な事とは、住宅が建つ、その敷地環境を
いかに設計に反映させて、有効な解決案を考案したか、に係っていると思います。
たとえば、住宅密集地で、自然の採光も通風もあまり期待できそうもない敷地
状況の中で、高断熱高気密の住宅を採用するという事は、理にかなっています。
それでも、有能な設計者なら、何らかの工夫を施し、光、風等の自然のエネルギ
ーを活用する方法を考えるのではないでしょうか。また、敷地周辺が自然環境に
恵まれ、光も風も十分に採り入れる事が出来るような場合、断熱、気密を設計の
第一義に置くことはないと思います。
「いい住宅」の定義はいろいろあるのだと思います。ただ、敷地環境であるとか、
すみ手のライフスタイルであるとか、そういったものと関係なく成り立つものでは、
決してないと断言出来るのではないでしょうか。
□ 200年住宅構想、もしくは住宅の寿命ついて
自民党+公明党政府が推し進める「200年住宅構想」がいよいよスタートするよ
うです。スクラップ&ビルドを止め、日本の住宅の寿命を今より長くし、社会資産と
して次世代 まで受け継がれるように、との趣旨は理解できます。
そのような超長期住宅を造るための指針として、政府が提唱するのが、構造体の
強化と将来に増改築が可能なような造り方、スケルトンとインフィルを分ける工法で
す。
さて、建築、住宅を造っているプロとして、自らが設計したものの寿命をなるべく
長く、人々に愛され使われて行く事を願うのは当然です。心ある建築家、設計士なら、
そのための配慮を、技術的に可能な限り、またはコストのゆるす限り、毎回施して
いることだと思います。
しかしまた我々は、どんなに構造的にしっかり造っても、また、将来的な増改築が
可能なフレキシブルな工法で建築を造っても、寿命を全うすることなく、解体されて
きた多くの建築、住宅があったことを知っています。どういう理由からでしょうか?。
住宅の基本設計の打ち合わせの時に、私はクライアントによく次のように言います。
「お子さん達がこの住宅で育っていって、いつか、独立して離れていったときに、彼等
が”僕たちの育った家は、とにかく魅力的ないい家だった。”と言えるような、彼等の
想い出に永遠に残るような、そんな住宅を造りたいですね。」
住宅に限らず、人がモノを長きにわたって慈しみ、使い続けているのは、人からの
愛情を受け入れられる”何か”があるからではないでしょうか。その”何か”は大量生産
されたモノには往々にして欠けている、強いて言えば、クラフトマンシップと呼ばれる
ものだと思います。たとえば、私が真心を込め描いた図面を基に、職人達が誠実に
彼等の技を入れ込んで出来上がった、オンリーワンの住宅にはその”何か”が宿って
いると信じています。
そのようにして住み継がれ、人々の心の中に残って行く住宅は、たとえ構造体が老
朽化して、メンテナンスにいくらかのコストが掛かろうとも、簡単には解体される事は
ないと思います。
つまり、そういう”何か”がないような住宅は、200年の寿命はないのだと、
そう思います。







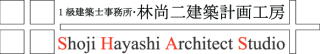
□ 「家相」「風水」家のバランスについて
家を建てるときに「家相」や「風水」が気になる人は、少なからずいます。
職業柄それらの事を知っていないといけないと思いまして、ずいぶん長い間
「家相」「風水」の事を研究してきました。
いま現在、私にとって「家相」「風水」とは、どういうモノであるのか?と問わ
れれば、一言でいって「家のバランス」であると、思っています。
中国で古くから信じられてきた「風水」は、基本に「陰陽五行」があります。
世の中の森羅万象全てを、何らかの形で我々に理解できるような整理の方法
思考方法、それが「陰陽五行」の基本だと思います。これから派生した「風水」
もよくよく観てみると、現在でいえば”バランス”を大切にしている考え方だと
思われます。
中国の「陰陽五行」「風水」が日本で流行し始めて、江戸時代に「家相」と
なって人々に伝わったということですが、この「家相」も、その当時のきわめて
合理的なバランスのよい家の建て方を、説いたものだと思います。
このあたりの事は、
清家清 著 「家相の科学」「続・家相の科学」
などの本に一番わかりやすく説明されています。
「家相」も「風水」も”吉”だとか”凶”だとかの言葉を使っていますので、何か、
宗教的な迷信めいたものがあるように思われますが、基本的には、「〜した方
がいいでしょう。」「〜しない方がよいでしょう。」と述べられている事柄だと思い
ます。
江戸時代の生活に合った家の建て方である「家相」を、そのまま現代に適用
しようとすると、当然無理があります。現代には現代の生活や家族構成にあっ
た「家相」があると思います。いろいろな人がいろいろ唱えている昔の「家相」は、
型とおりに信じない方がいい場合が多いように思われます。
たとえば、私はこれまでテレビなどで報道された、家庭の中で起こった不幸な
出来事の、その家の間取りを調べて、研究したことがあります。埼玉の中学生の
首つり事件であるとか、神戸のサカキバラ事件であるとか、母親殺害の事件で
あるとかです。それらの住宅の間取りを観て、共通していることは、見事に昔の
「家相」通りの間取りだったと言うことです。言い換えれば、現代の生活に合って
いないバラスの悪い間取りです。
家造りに一番大切な、その家族の暮らし方にマッチし、周辺の環境や敷地の
状況に適応している”バランス”のよい家を造る、そのことが、現代の「家相」に
一番適合している、そういう事だと思います。